
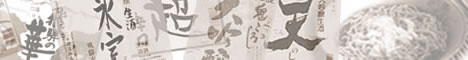
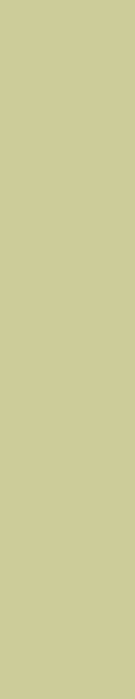
| HOME | > | 飛騨高山の歴史 |
歴史 飛騨高山の歴史をご紹介します。
地勢・気候 縄文〜古墳時代 白鳳・奈良時代 平安時代〜戦国時代 金森時代 幕府直轄地(天領)時代 明治以降
| 飛騨は険しい山の中、山が襞(ひだ)のように重なり、その間に狭い谷が幾筋も伸びています。 そこにはポツンポツンと山村集落が散在していますが、その中に、飛騨では最も古い高山、国府・古川盆地が広がっています。 初めて高山を訪れる人は、飛騨へ向かう途中で、こんな山奥に果たして家があるのだろうかと不安になるでしょう。しかし高山本線で分水嶺の真下を宮トンネルで抜けると、あるいは、国道41号線で宮峠を越えると急に空が広くなります。やがて高山の街に入り、山の中にこんな大きな町があることに驚くのです。 飛騨は日本列島のほぼ中央に位置し、古くは縄文時代から東西南北の文化が押し寄せ、複雑に交錯しあい、発展をしてきました。気候は内陸性盆地型気候で、昼夜、真冬の気温差が大きく、湿度は低くなっています。冬は大変寒く、サラサラとした雪が舞い、冷え込むときは氷点下15度までも下がることがあります。夏は日中まぶしくて目を開けていられないくらい日差しが強いことが多く、それでいて湿度は低くカラッとした爽快感(そうかいかん)が味わえます。夜は大変涼しくなり、布団をかけて寝なければ風邪をひいてしまうほど、気温が下がることがあります。 高山盆地からは東に乗鞍岳、穂高岳、槍ヶ岳、西に白山、南に御岳山(おんたけさん)が遠望でき、風向明媚なところが随所にあります。さて、このような風土の中で、どのような歴史が生まれてきたのでしょうか。 |
飛騨には縄文時代の遺跡が非常に多くあり、随分古くから文化が開かれていたことが想像されます。 |
| (飛騨の匠) 今から1350年ほど前、大化改新によって税を収めることが決められました。飛騨は山国で、納める米や織物が少ないため、そのかわり1年に250〜300日間、都へ行って働くことになりました。 都では、宮殿や門、寺院などを造る大工仕事をしました。家50戸ごとに10人ずつ割り当てられ、飛騨からは100人前後の匠が出て行ったのです。 匠たちは、木の豊富な飛騨に生まれ育ったから、大工仕事はお手のもの。飛騨の匠の手にかかって、立派な建物ができ上がっていきました。 しかし、なかには仕事が苦しくて逃げ出す人もあったといいます。歴史上にも、有名な寺社を建てた人の中に、飛騨の匠の名前が数多く見られます。匠たちは飛騨へ帰って「三仏寺廃寺」など飛騨の古代寺院造営にその技術を生かしました。 奈良時代には、はっきりとした形で、中央の文化が高山へ入ってきます。その事実を示すものは、国分寺と国分尼寺です。およそ1200年前、聖武天皇は仏教を盛んにしようとしていました。そして、各国に国分寺を建てるように命じました。高山の国分寺には、建立されたときの塔の礎石が今も残っています。境内にそびえたつ大きなイチョウの木も、当時のものです。ただ残念なことに、奈良時代創建当時の建物は残っていません。現在ある本堂は、500年ほど前に改築されたものです。また、国分尼寺も辻ケ森三社境内地に発見され、市の史跡に指定されています。 |
| 平家が天下を握ると、飛騨は平家の領国になりました。 その中心は現在の高山市三福寺(さんふくじ)町といわれ、三福寺には三仏寺(さんぶつじ)城(県史跡)が築かれました。鎌倉時代の高山は不明なことが多く、おそらく政治の中心が高山市の北方、吉城郡(よしきぐん・現在の国府・古川町)の方へ移ったと考えられています。 室町時代の終わりに高山外記(たかやまげき)が、天神山(てんじんやま・今の城山)に城を築いていました。そのため、高山外記の城の近くを高山と呼ぶようになったとも伝えられています。戦国時代になると、高山の南にあたる益田郡に勢力を持っていた三木(みつき)氏が、高山へ進出し、松倉城を築きました。この頃、日本の国は豊臣秀吉がおさめるようになりましたが、三木氏は秀吉に従わず、秀吉の家来の金森長近に滅ぼされてしまいました。 |
| 豊臣秀吉は天正13年(1585)7月に越中の佐々成政(さっさなりまさ)を攻めました。 その際、越前大野城主であった金森長近は、飛騨の三木氏攻略を命ぜられています。 長近は同年8月、三木氏の松倉城を攻め落として飛騨を平定しました。そして天正14年8月7日、長近は飛騨国3万3千石の国主として入府しました。また関ヶ原の戦いでは徳川方について前線で戦い、美濃国上有知(こうずち・美濃市)1万8千石、河内国金田(大阪府)3千石を加増しています。入国した長近は、城の建設を天正16年(1588)から始め、慶長5年(1600)までの13年間で本丸、二之丸を完成させ、以後3年かけて三之丸が築かれました。日本国中に5つとない見事な城だと記録が残っています。また、城と同時に城下町の工事も行われています。城を取り囲むように高台を武家地とし、一段低いところ(三町)を町人の町とし、京都になぞらえて東山に寺院群を設けました。農民一揆の対策としては、門徒の多い照蓮寺(現在の高山別院)を高山城と向かい合わせに配置し、人の心を安め、宗和流茶道を始め、寺社の再興、様々な文化をおこすことも積極的に行ったのです。 高山における金森氏は6代107年間続きましたが、元禄5年(1692)7月28日、頼とき(よりとき)の時代に突然、出羽国上ノ山(でわのくにかみのやま・山形県)に転封となって金森氏による政治は終わったのです。 頼とき(よりとき)は上ノ山に5年間居ましたが、元禄10年(1697)、今度は美濃国上藩に転封となりました。頼ときは江戸芝の屋敷で亡くなり、孫の頼錦(よりかね)が後を継ぎ、幕府の奏者役を命ぜられました。そのため多くの費用を必要としたこともあり、年貢を定免(じょうめん)法から検見(けみ)取りに改めたため、4年半にわたる「宝暦郡騒動]が起こっています。 これで金森の本家はとりつぶされてしまいましたが、分家の旗本左京(さきょう)家は、3千石のまま越前に領地替えになり、現在も武生市に子孫が在住しています。 |
| 金森氏移封後の飛騨は幕府直轄地となり、代官には関東郡代・伊奈半十郎忠篤が兼任、金沢藩主前田綱紀(つなのり)が高山城在番を命ぜられました。 元禄8年(1695)1月12日、 幕府から高山城破却の命令が出され、同年4月22日から取り壊しを開始、6月18日には全てを終えて帰藩しました。 今は「高山城跡」として県史跡に指定され、緑豊かな城山公園になっています。幕府直轄地時代は、25代、177年間続き、11代までが代官、12代大原彦四郎から郡代に昇格をしました。明和8年(1771)、大原代官は幕府の命令で飛州全山に官材の元伐(もとぎり)を中止、安永2年(1773)には飛騨の村々の代表を集め、検地のし直しを言い渡しました。飛騨の農民たちは田を少ししかもっておらず、新しい年貢がさらに厳しくなると越訴(おっそ)、駕籠訴(かごそ)などをして検地中止を願い出ました。ここに明和8年(1771)から寛政元年(1789)までの大原伏し 代、18年間にわたる農民一揆が起きたのです。その中に主な事件が3つ含まれていて、明和、安永、天明騒動と名づけられています。 明和・安永騒動では9千人余の農民が罰せられ、大原彦四郎代官は飛騨を5万5千石に増石した功績により郡代に昇格しました。しかし、天明騒動では大原亀五郎郡代の政治不正が問われて、郡代は八丈島へ流罪、農民側の罪は軽くて済んでいます。 善政をつくした代官・郡代もいます。7代長谷川忠崇(ただたか)は『飛州志』を著しています。。第8代幸田善太夫(こうだぜんだゆう)は飢饉のために馬鈴薯(ジャガイモ)を農民に作らせ、飛騨では、「善太夫(ぜんだゆう)いも」、「せんだいも」とも今も呼んでいます。 19代大井帯刀(たてわき)は天保飢饉の際に、飛騨はもちろん出張陣屋(越前本保)領内でも救済措置を講じました。20代豊田藤之進(とよたふじのしん)は渋草焼を起こし、養蚕を盛んにしました。 |
| 明治維新により東山道鎮撫使竹澤寛三郎(とうざんどうちんぶしたけざわかんさぶろう)が入国し、高山陣屋に天朝御用所の高札を建てました。 明治元年5月に飛騨県がおかれ、同年6月高山県となり、明治4年(1871)筑摩県に移管されるまでの3年6カ月間、梅村速水、宮原積の二人の知事により治められました。 明治元年(1868)3月3日、水戸藩の梅村速水は高山に来て、県知事になりましたが、古いならわしになれた高山の人たちは、梅村の急激な改革には到底ついて行けず、梅村騒動という一揆を起こし、梅村知事を追い出してしまいました。 明治8年に高山一之町(いちのまち)村、二之町(にのまち)村、三之町(さんのまち)村が合併して高山町になりました。明治9年飛騨は岐阜県にはいり、明治22年(1889)には15,385人で新しい町制が実施され、大正15年(1926)に灘村を合併。昭和9年(1934)国鉄高山本線が開通して、高山の近代化が急速に進みました。昭和11年、(1936)に大名田町を合併して高山市となり、昭和18年(1943)上枝村(ほずえむら)、昭和30年(1955)に大八賀村(だいはちがむら)を合併し、現在の高山市となったのです。 |
飛騨高山観光情報 (高山市公式ホームページより転載)http://www.hidanet.ne.jp/takayama
| HOME | > | 飛騨高山の歴史 |